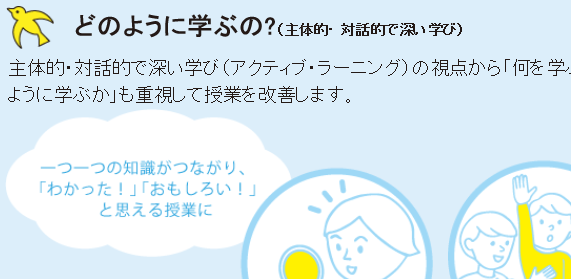文部科学省の方でも,カタカナ言葉の採用には慎重な立場をとるため,この「AL」の方は表に出したり引っ込めたりしながら,新学習指導要領の告示を迎えた経緯があります。
本文からは姿を消したものの,『総則』の解説編や水色に黄色い鳥があしらわれた周知パンフレット(写真)では( )に収めて添えられる形で落ち着きました。
「AL」はもともと,講義中の大学の学生たちに居眠りをさせないために,主体的に参画させるノウハウを検討する中で生まれた発想です。さすがに小学校で居眠りをしている児童はそんなにいるわけもなく(ゼロではありませんが),小学生にとっての「主体的・対話的で……」ってどういうこと? というようなことを考えながら教室を回っています。
写真を左上からたどっていくだけでも……作業を伴う学習(1年算数),表現活動(2年音楽),映像上でシミュレーションしながらの学習(3年算数),話し合い(5年道徳),発想構想のひと時(6年図工),観察実験(5年理科),学習成果の共有(6年算数)……という具合に,もちろん居眠りなどする暇もなく「主体的・対話的」な学習が展開されています。
あとは,これに「深い学び」がどう伴うか……ということになります。これには,学習内容が本当の意味で「自分ごと」になっていかなければならないのだろうな……と思います。すでにそうなっているケースも,もちろんあるのですが。
「深い学び」と「自分ごと」についてはまた改めて,話題にしていきます。